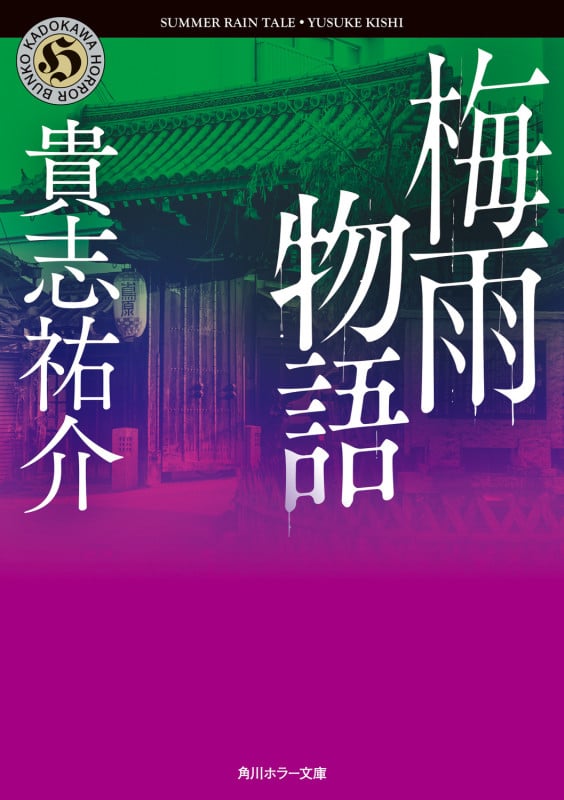『梅雨物語』
貴志祐介/2025年/400ページ
謎を解くたびに、絶望は深まる。貴志祐介が描くホラーミステリの極北 。
自ら命を絶った青年が残したという1冊の句集。元教師の俳人・作田慮男は、かつての教え子から依頼を受け、俳句の解釈を進める。沖縄の情景を描いた句を読み解いていくうち、恐るべき秘密が浮かび上がってくる(「皐月闇」)。遊廓で蝶のような花魁たちと遊ぶ夢を見る男の末路、広い庭を埋め尽くす色とりどりのキノコがもたらす幻覚。静かに忍び寄る恐怖と緻密な謎解きが読者を圧倒する3編を収録。著者真骨頂のホラーミステリ。
(Amazon解説文より)
「皐月闇」-教職を引退した作田慮男のもとへ、かつての教え子・萩原菜央が訪ねてきた。自ら命を絶った兄・龍太郎の遺作である句集「皐月闇」を、俳人でもある作田に読んでもらい、感想を聞きたいというのだ。やや不気味なタイトルにそぐわず、「皐月闇」の中身は凡庸な句ばかりだったが、作田は沖縄旅行を題材にした一連の句から、ある恐ろしい真実を導き出す…。
俳句が手掛かりとなるミステリは、かの有名な『獄門島』をはじめ意外と多いのだが、本作の場合は解き手である作田が認知症を患っており、肝心なことを思い出せないという点がユニーク。なにげない平凡な句に隠された“意味”を解き明かしていく過程はなかなかスリリング。わずか17文字が取り返しのつかない現実を突きつけてくる、最後の一句がまた怖い。
「ぼくとう奇譚」ー高等遊民の木下美武は、友人の桑原清吉と訪れた銀座のカフェーで「最近、黒い蝶が現れる夢を何度も見る」という話をしていた。カフェーを出ると千里眼の行者を名乗る男・賀茂日斎が現れ、「黒い蝶が、お主を導く先は、地獄の他ない!」と一喝する。その日以降、日斎の描いた御札を貼って寝ることにした木下だったが、日斎の使いで彼の様子を見に来たという住職・日晨は、木下を見て「黒い蝶は悪霊などではなく、この後に訪れる真に恐ろしいものを警告しにきている」と語る。その夜、木下は黒い蝶に導かれ、7人の花魁が待つ楼閣を訪れる夢を見た。日晨が言うには、呪いを解くためにはこの花魁の中からたった1人の正解を選ぶ必要があるのだという…。
舞台は昭和初期で、「濹東綺譚」の作者である永井荷風もチラリと登場する。濹東ならぬ“ぼくとう”が示すものとは、7人の花魁とは何者なのか、そして木下を呪う相手の真意とは…。あまりにもおぞましい一編で、この「おぞましさの正体」が露わになってくる終盤はまさに悪い夢そのものである。その「正体」に比べれば、作中の花魁だの武士だのといった怪異はむしろ可愛らしい部類だ。
「くさびら」-妻と息子に出て行かれた杉平信也は、軽井沢の家でひとりテレワークを続けていた。ある日、庭のあちこちでフェアリーリング状にキノコが生えているのを見つけるが、それらはすべて杉平の幻覚だった。従兄弟で精神科医の鶴田、義母が雇った探偵の末広は、必死の形相で庭を掘り返す杉平をいぶかしげな目で見つめるのだった。なぜ自分が幻覚を見るのか思い悩む杉平は、かつての同級生で今は山伏として活動している猪口に祈祷を頼む。大がかりな祈祷の儀式を胡散臭げに眺めていた鶴田だったが、この状況が狂言の演目「茸 (くさびら)」に酷似していることに気づく…。
姿を消した妻と息子、キノコの幻覚を見て庭を掘り返す男。読者の頭に浮かぶのは“最悪の想像”だろうが、果たして実際は…。本書のベストを選ぶならこの1編だろう。多くは語れないが「見事」の一言。
『秋雨物語』と比較すると、本書はミステリ寄りのホラーが多め。3編とも主人公の男性の「過去」が、さまざまな理由で明らかにされておらず、読者目線ではあまり信用のおけない人物であることが共通している。謎解きのカタルシスを台無しにするほどに暗鬱で陰惨な雰囲気が漂っているが、不思議と読後感はカラっとしている。
★★★☆(3.5)